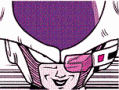大好きな叔母と、叔母に瓜二つな従妹と葬儀で再会した母娘丼体験
叔父はお袋と少し年の離れた弟だったので、お嫁さんになったばかりの叔母は当時まだ二十歳を過ぎた頃で、ボクはと言えば小学校に入ったばかりの頃だった。
都会というには少しおこがましい中途半端に開けた街に嫁いできた叔母は、子供の目にも垢抜けていて、それまで接してきた大人とは身なりも身のこなしもちょっと違った雰囲気を醸していた。
大人なのにセミロングのおかっぱ頭で、アーモンドのような涼しい眼をした叔母はまるで別の世界から来た人のようだった。
まだ子供のくせに、ボクはそんな叔母の綺麗な顔立ちと、母や周りにいる他のおばちゃんたちとは違って細くて、それでいて胸の大きな叔母が大好きだった。
自分の容姿が標準以下であることに気づいていなかった頃、そんなボクは結婚したばかりの叔母に纏わりついて
「一緒にお風呂に入りたい」
とせがんでみたり、叔母の腰に抱きついてみたりしては叔父に冷ややかな目を向けられていたのが子供心にも分かっていたのだけれど、叔母は嫌がりもせずにボクをお風呂に入れてくれていた。
一緒に湯船に浸かりながら無邪気なふりをして叔母のおっぱいに触ったり、背中から抱きついてみせたりした。
極めつきには、黒い草むらを目の当たりにした時には股間が何だかもぞもぞしていた。
しばらくして従妹が産まれて、それからも10年くらいは近所に住んでいた叔父一家だったが、その後、叔父の仕事の関係でボクの田舎とは別の地方に引っ越してしまった。
叔母に会えなくなったのは残念だったけど、ボクはボクで大学に入ってから実家から足が遠のいて田舎に戻ることも滅多になかったので、それからはすっかり疎遠になってしまった。
月日は流れ、次に叔母と顔を合わせたのは、なんと叔父の葬儀でのことだった。
訃報は突然舞い込んできた。
母親からの電話で知ったのだけれど、それは晴天の霹靂だった。
けれども突然に思えたのはボクだけで、叔父はもう一年も入院していたとのことだった。
叔父はまだ40代だったのに、治療の甲斐も虚しく病魔に倒れた。
告別式の日、叔母は喪服に身を包み、凛として葬儀の場で喪主の勤めを果たしていた。
最後に会った時からもう何年も経っているのに、叔母は相変わらず綺麗だった。
普通の世間一般のお母さんたちのように脂肪を蓄えることもなく、背筋をピンと伸ばして佇む姿は、むしろ大人の色気を身に纏って、以前よりも綺麗だった。
でもその表情は少し青ざめて、やつれた感じがしていて妙に色っぽかったようにも思う。
隣には、若い頃の叔母と瓜二つの従妹が高校の制服姿で涙を堪えて立っていた。
葬儀はしめやかに執り行われたが、不謹慎にもボクは式の間中、叔母の姿をずっと目で追っていた。
何度か叔母と目が合って、何だか気まずくてボクはその度に視線を逸らしていた。
葬儀の後の宴席で寿司をつまんでいると、従妹のアズサがボクのところにビールのお酌をしにやってきてくれた。
ボクは親戚筋の冠婚葬祭にはほとんど縁がなく、昔から知っている親戚の顔は限られていて、会場でも半分ぐらいしか誰が誰なのか区別がつかなかったので、知っている顔が近づいてきてくれたことがありがたかった。
ボクが懐かしそうにその娘の顔を見ていたからだろうか、アズサはクスリと笑うと、
「トモくん、会うのは久しぶりだよね」
叔母と同じ呼び方で、そう言いながらビールを注いできた。
アズサの顔に、もう涙の跡はなかった。
「アズサちゃん、かなり痩せたよね?」
「うん、少しはいい女になった?」
「うん、叔母ちゃんとそっくりだもん。驚いたよ」
「お母さんに似ているってことは褒められてるんだよね?」
「もちろん」
ボクが自信を持ってそう言うと、屈託のない笑みを浮かべたアズサは、
「ご無沙汰してます」
と言って改まったようにボクに頭を下げた。
「でも、ホントにアズサ?」
「いやだ・・・、私、そんなに変わった?」
「いや・・・、うん。昔のアズサはもう少しふくよかって言うか、味噌っ歯っていうか・・・」
アズサは口元に手を当ててフフッと笑うと、
「トモくん、もうあれから8年も経つんだよ」
と言った。
「あれから歯科矯正もしたし、背も髪も伸びたから」
「そうだね。昔はもう少しポッチャリしていたし・・・」
「また、それを言う・・・。あれはトモくんがしょっちゅう焼きそばパンを食べさせたからじゃない」
ボクが言い終わらないうちにアズサは被せるように抗議した。
「食べさせたとは人聞きが悪いなぁ。アズサがいつも一口くれって言ってたんじゃないか」
「子供相手なんだから、どっちだって一緒でしょ。食べさせたことに変わりはないんだから」
そう言って人差し指を横にして鼻の下に付けて笑うアズサの口元には矯正された綺麗に並んだ白い歯がこぼれていた。
昔は叔母と同じくおかっぱ頭だった髪が、背中まで伸びていた。
高校生の頃、ボクはインスタントの焼きそばにハマっていて、それを食パンに挟んでは焼きそばパンと称して三日と空けずに食べていた。
プライパンを取り出して焼きそばを作り始めると、アズサはどこからともなく物音を聞きつけてきて台所にやってきて、ボクが作るのを背後から黙ってじっと眺めていた。
アズサはあまり外で遊ばない子供で、気がつくと何故だか我が家でうろうろとしていることが多かった。
子供に見られているのに1人で食べるわけにもいかないので、社交辞令として
「食べる?」
と聞いてやるのだが、アズサはそれを断ったことがなかった。
一度、
「アズサが太って、思春期にいじめられたら、トモくんのせいだからね」
と叔母に釘を刺されたことがあったが、アズサはいつもボクのところにやってきた。
実際のところ、アズサとボクは結構ウマが合って、よく話をした。
一時は歳の離れた親友のようだったとも言えるかもしれない。
ボクも友達が少なかったので、似たもの同士だという意識でそうなっていたのかもしれない。
それに、ほんの少しだけ2人の秘密も持っていた。
アズサはまだ小学生だというのに頭のいい子で、気がつくとボクの部屋に忍び込んできてはボクの蔵書をよく漁った。
ところがある日、ボクの部屋の押し入れに隠れて懐中電灯の明かりを頼りに何かを読みふけっているアズサを見つけた。
アズサはいつの間にかボクの秘蔵のエロ雑誌を探し出して夢中になっていた。
微かな物音に気づいて押し入れの扉を開けた時、アズサはスカートの中に手を入れて下着の上から股間を触っていた。
それを見たボクは驚いたが、アズサは自然に手が伸びていたらしく、ボクに見られても恥ずかしがる風でもなく、雑誌に釘付けになったまま細かく手を動かしていた。
「アズサ、何を見ているの?」
「エッチな写真」
アズサは悪びれもせずに言った。
「アズサ、そうすると気持ちいいの?」
「ん?わかんない・・・」
「人前でそんなことをしたらダメだよ」
「そうなの?」
アズサは股間を触っていた指を自分の鼻に近づけてクンクンと少し嗅ぐと
「臭い」
と小さく呟いた。
その頃のアズサはどちらかと言うと少しムッチリした女の子で、最近の女の子みたいに細い体型とは言えない女の子だった。
そのくせ叔母に似たのか目鼻立ちははっきりしていて、小学生とは思えないような色気を感じることがあった。
しかも好奇心は旺盛で、ボクに対してそれを真っ直ぐにぶつけてくるのは微笑ましいのだが、性的な関心もぶつけられるのにはちょっと閉口した。
「ねぇ、おちんちんって大きくなるの?」
「私もセックスすると気持ちよくなるの?」
「トモくんもセックスしてるの?」
無邪気な女の子の疑問と言えばそれだけかもしれないが、ませていると言えばませた女の子の質問でもあった。
ボクも叔母に対してそう見えていただろうから、これは我が家の家系なのかもしれない。
「トモくん、私、4月から上京して下宿をするから何かあった時はよろしくね」
アズサの声でボクは記憶の世界から引き戻された。
「え?アズサ、東京に住むの?どうして?」
「もう、トモくん、何を聞いてるの?大学受かったって言ったじゃない」
「そうか、ごめんごめん」
「だからトモくん、携帯の番号を教えておいて」
そう言われて番号を交換したが、サナギから蝶のように綺麗な娘に変身したアズサと冴えないボクが連絡を取り合うことになるとはその時は夢にも思っていなかった。
色気はあってもまだ子供だった当時のアズサに対して、性の対象としての食指はさほど動かなかったが、色々と相談には乗ってやった。
ボクの部屋で見つけた雑誌を読んで覚えたのか、
「ねぇ、クンニってなに?」
「オルガって気持ちいいの?」
「トモくん、どんな風になるのか教えて・・・」
アズサの知的好奇心はどんどんエスカレートして行って、正直なところボクは困ってしまった。
とは言え、当時まだ高校生だったボクは全く女の子にモテなくて、今でもモテないのだが、色々と聞いてくるアズサに教えてやりながら、結局はアズサに女性の身体について勉強させてもらっていたことになる。
その頃のボクは、本当はまだクンニもオルガも言葉の上でしか知らなくて、
「じゃあ、下着を脱いで見せてごらん」
と言って割れ目を見せてもらって小さな突起を指で撫でては、
「これがクンニだよ」
などといい加減なことを言っていた。
叔母に似たのか、アズサは小学生とは思えない体格の良さでまさに健康優良児だったが、まだ生理もなくて陰毛も薄らと生えている程度だった。
けれども何度か2人の秘密の時間を過ごすうちに、幼い亀裂でも濡れてくることがわかった。
そして、その時はやってきた。
「トモくん、なんだかヘン・・・」
ボクに敏感な突起を擦られながら、アズサは目をトロンとさせた。
半開きの口になったまま、目を閉じて、
「あ、そのまま・・・、もっと優しく続けて・・・」
「あ、あ、あ、私、なんかヘン・・・」
「ねぇ、なんかヘンだよ・・・、はっ、はっ、はっ、はっ、あ、うっ!」
ボクの愛撫を受けてアズサはお腹にグッと力を入れたかと思うと身体がビクッとなって、そのまま背中を丸めた。
「大丈夫か、アズサ?」
声を掛けると、アズサは肩で息をしながら顔を上げ、
「トモくん、これがオルガ?」
と少し潤んだ目を向けて訊いてきた。
経験の浅いボクはよく分からなかったのだけれど、
「そうだよ」
と思わず答えてしまった。
アズサはそのまま余韻に浸っていたようだったけれど、やがて身体を起こすと小学生とは思えない吃驚するような妖艶な目をしてみせた。
「トモくん、大好き」
ニッと笑って、そういいながらボクの首に抱き付いてきたので、ボクはアズサの背中に手を回してそっと抱きしめてやったのを覚えている。
それから何度もアズサには女の子の身体を見せてもらった。
小さなおっぱいの先についた小さな乳首が勃起するのも神秘的な気がした。
ボクはアズサにオナニーを教えてやって、どうすると気持ちいいのか、アズサの身体を使って2人で研究した。
アズサの幼い亀裂からはもっとたくさんの粘り気のある愛液が溢れ出すようになった。
何度か割れ目に沿って指を這わしていくと、子供のくせにアズサの小さな突起は明らかに膨らみを見せていた。
捏ねるように刺激してやると必ずイクようになってきた。
「トモくん・・・、あ、あ、あ、あ、あ・・・、何だかヘン・・・、あー、震える、震える、震える、あ゛ーっ」
そう言って腰をガクガクさせたかと思うと顎を上げて仰け反り、果てて行った。
アズサは絶頂に達した後、必ず、
「トモくん、トモくん」
と言っては甘えてきて、ボクに抱き付いてきた。
ボクはそんなアズサを腕の中に抱きしめて、いつかは大人の女性とセックスできるのだろうかと叔母の姿を想像しては自分で自分を慰めた。
幼いアズサとセックスをする気はなかったけれど、一度だけアズサの幼い小さなお口に亀頭を含んでもらって射精してしまった。
オルガのあと、いつまでもボクの股間の膨らみを撫でていたアズサの誘惑に勝てず、ボクは下着ごとズボンを下ろすと何の躊躇いもなくパクリと小さなお口に咥えられた。
アズサは幼い舌で一生懸命に舐めてくれて、ボクが出した後もゴクリと喉を鳴らしてザーメンを飲み込んで、
「女の人が飲んであげると、男の人は嬉しいんでしょう?」
とませたことを言った。
こんなに小さくてももう自分が女の人だという自覚があるのだななどと思いながら、そんなアズサのことがいじらしくていつまでも抱きしめてやった。
けれども叔父一家の引越しで、そんなアズサとの秘密の時間もそれっきりになってしまった。
「もしもし、トモくん?私、アズサ」
アズサからボクの携帯に電話がかかってきたのは、葬儀から1カ月ほどが経ってからだった。
「どうした?何かあったか?」
「ううん、この間トモくんの顔を見たら、また声が聞きたくなっちゃって・・・」
すっかり綺麗になった女子大生が冴えない従兄に何の用だろうと思いながら用件を切り出すのを待っていると、
「ねぇトモくん、お買い物に付き合って・・・」
と言われた。
"大学に入ったのだから友達は大勢いるだろうに"
そう思ったが、綺麗な従妹と街を歩くのも悪くないなと思い直して一緒に出掛けることにした。
本当のことを言うと、2人の秘密の時間のことを思い出して、ちょっとだけいけない想像もしていた。
待ち合わせ場所に着くとアズサは先についてボクを待っていてくれて、ボクの姿を見つけると子供のように手を振った。
「待った?」
「ううん、私も今来たところ」
アズサはまだほとんどお化粧をしていなかったけど、薄手の長袖のブラウスにタイトなジーンズ姿で、春らしいパステルカラーのカーディガンを肩に羽織った姿はコンビニに並んでいる女性誌の表紙にできそうな姿をしていた。
「何を買いに行きたいの?」
そう聞いてもアズサはもじもじしているだけで要領を得ない。
とりあえず繁華街の方向に向かって歩き始めると、アズサはボクの肘に自分の腕を絡めてきて一緒に歩き始めた。
昔よりも大きく膨らんだアズサの胸が肘に当たるのを感じて、心の中でボクは"ラッキー"と思ってしまった。
すれ違う人の何人かがボクたちを振り返って見ているのがわかった。
今や国民的美少女と言ってもいいような蝶々の姿になったアズサがイケてないボクと歩いているのだから無理もなかった。
「ボクたち、美女と野獣だと思われてるよ」
恥ずかしくなって隣を歩くアズサにそう語りかけると、アズサは目を伏せながら、
「トモくん・・・、じゃあ、人目のつかない2人きりになれるところへ行く?」
と言ってきた。
「えっ?」
驚いて思わず足を止めると、勢いのついたアズサの身体、というよりも胸がボクの腕に一層強く押し付けられて何だかドキドキした。
「それって、ラブホとかのことを言ってる?」
まさかと思いながらも、冗談のふりをしながらも少しだけ期待を込めてそう尋ねると、アズサは上目遣いにボクの顔を見ながらコクリと頷いた。
舞い上がってしまったボクはどこをどう通って辿り着いたのかよく覚えていないが、気がついたらボクたちは2人きりでホテルの一室にいた。
部屋にはキングサイズのベッドがあってボクは結構うろたえてしまった。
「トモくん、あんまり経験無いの?」
図星だった。
それと若さのせいだろうか、従妹とは言えども綺麗な女性にストレートな質問をぶつけられてボクはちょっと傷ついた。
ボクの表情を素早く読み取ったアズサはボクの肩におでこを当てて、
「トモくん、ゴメンなさい」
と素直に言った。
「アズサみたいに世の中の人がみんな恵まれているわけじゃないんだよ」
ボクがやっとのことでそう言うと、
「トモくん、そういう意味じゃないの。私、ずっとトモくんのこと想っていたから、あれからどうしていたのか気になっちゃってて・・・」
「この顔でモテると思う?」
そう言った途端、アズサはボクの首に抱きついてきて、
「よかったぁ」
そう言うとボクをベッドに押し倒して唇と重ねてきた。
何がよかったのか複雑な心境だったが、アズサと抱き合うとそんな思いはすぐにどこかへ行ってしまった。
長い間お互いの唇を吸い合っていたが、アズサが唇を離して大きく吐息を吐いた。
「私、初めてなんだ。優しくしてね」
アズサは少し恥ずかしそうに、ボクの胸に額を押し付けながらそう言った。
ボクは一層舞い上がってしまってアズサのブラウスのボタンを外す時に手が震えてしまった。
アズサはボクの手に自分の手を重ねてきて、
「ずっとこの日を待ってたんだよ」
そう言ってくれた。
何とか全裸になったアズサをベッドに寝かせて覆い被さると、早くも痛いほどに屹立した肉棒の先端をアズサの亀裂にあてがった。
初めてだと言っていたのに、アズサの茂みには既に雫がついていて、亀頭はすんなり呑み込まれた。
アズサの様子を窺いながら、ゆっくりと中に入って行った。
「痛くない?」
初めてと言う割にはすんなりと奥まで入ってしまってからアズサに囁くと、
「少し・・・、でも大丈夫」
と目を閉じたまま答えた。
そのままゆっくり、ゆっくりとアズサの中で往復すると直ぐに射精感が襲ってきた。
直ぐに終わってしまうのが恥ずかしくて、ボクはできるだけ堪えた。
けれども限界はあっという間にやってきて、ボクは慌ててアズサの中から抜くと平らなアズサのお腹の上に白濁液を散らした。
「あったかぁい・・・」
それがアズサが最初に漏らした感想だった。
アズサは自分の臍に貯まった半透明の液体に指で触れた後、クンクンと匂いを嗅いで、
「懐かしい・・・」
と一言漏らした。
枕元のティッシュを取って、アズサのお腹を拭いた後、自分のモノを拭うとアズサに腕枕をした。
「あんまり血が出なくてよかったね」
そう言うと、アズサはボクの腕に唇を押し付けながら、
「でも、私、初めてだよ」
と言ったので、
「うん、ボクなんかを初めての人に選んでくれてありがとう」
そう言うと、アズサはボクの腕を枕にしながら仰向けになった。
しばらく続いた沈黙を破ったのはアズサだった。
「あのね・・・」
「ん?」
「私、トモくんに教えてもらってから・・・、やめられなかったの・・・」
「え?」
「うん・・・、その・・・、トモくんと会えなくなってから、自分でイクことも覚えちゃったし・・・、指を入れちゃったときに血が出ちゃって・・・。自分でも驚いちゃって、処女じゃなくなっちゃったと思って悲しかったけれど、トモくんとこうなれた時にはきちんと話をしようと思ってたの・・・信じてくれる?」
整理のついていないアズサの話を聞きながら、
「うん、アズサが嘘を言う理由なんてないもん。信じるよ」
そう言うと、
「ありがとう、嬉しい!」
アズサはそう言うと身体を横にしてボクに抱き付いてきた。
身体は細くなったけど、アズサの胸はふくよかでそれが身体に触れてくるだけでボクの胸はドキドキした。
アズサは結婚した頃の叔母を少し幼くしたくらいにそっくりで、アズサを抱いているとあの頃の叔母を抱いているような錯覚に陥った。
けれどもボクにとって大事なのは、永遠の憧れのマドンナよりも目の前の現実の女の子だった。
子供の頃からの恋心の対象が母親から娘に移るなんて何だかずるい気がしたが、アズサとの時間が長くなるに従って、そんな思いは徐々に薄れていった。
そして、大学2年になる前の春休みのことだった。
アズサは大学の友達と旅行に出かけた。
ボクを心配させないように一緒に行くのは女友達3人だとアズサはきちんと教えてくれた。
アズサのいない週末に家でゴロゴロしていると、古いマンションの入り口のインターホンが鳴った。
誰だろうと思いながらモニター越しに見てみると叔母だった。
驚きながらも急いで入り口の解錠ボタンを押すと、1分も立たないうちに叔母はうちの玄関の前に立っていた。
葬儀の時の喪服とは違って、叔母は淡いブルーのブラウスにカーディガンを羽織っていて、白いフレアのスカートの裾には紺のストライプが入っていた。
「トモくん、お邪魔してもいい?」
玄関の扉を開けると挨拶もなしに叔母は言った。
勢いに押されて叔母を招き入れると、ボクは寝室に先回りをして、ベッドを片付けた。
叔母はその間にバスルームを覗いていて、ボクのものと一緒に女物の下着が干してあるのを見られてしまった。
「アズサはよく来るの?」
ボクが勧めた座布団に膝を乗せるなり、叔母は聞いてきた。
女物の下着があったって、アズサのものとはわからないと思ったけれど、ボクは観念した。
「うん、週に一度くらいかな」
本当は週の半分以上、アズサはボクの部屋に入り浸っていたのだけど、そうは言えなくてかなりサバを読んでしまった。
叔母は深いため息をつくとボクの目を覗き込んできた。
ボクは思わず目を逸らしてしまい、
「あ、お茶を淹れるね」
と言って立ち上がろうとした。
でも叔母はそんなボクを目で制し、もう一度座らせると言った。
「トモくん、どういうつもり?」
「え?」
「"え?"じゃないでしょう。アズサのこと」
「いや、それは・・・」
「アズサはまだ子供なのよ」
「でも・・・」
「"でも"、なに?」
「いや、その・・・」
ボクがモジモジしていると、叔母は少し姿勢を正し、
「どうして、もっと勇気を出して叔母ちゃんのところに来てくれなかったの?」
と言われた。
「えっ?」
思わず顔を上げて叔母に視線を戻すと、叔母は急に優しい顔になって、
「トモくん、アズサに私を重ねて見ないで」
と言うとボクのそばににじり寄ってきて、ボクの首の後ろに手をやると自分の胸に軽き引き寄せた。
「えっ?えっ?」
ボクはどうしてそうなるのかよく解からなかった。
けれどもボクの股間は正直で、小さい頃から大好きだった叔母の豊満な胸に顔を埋めたせいで、ジーパンの中で膨張したイチモツは締め付けられるのを感じた。
「お、叔母ちゃん・・・」
そう言った途端にボクの唇が塞がれた。
叔母の舌がヌルリと入って来て、直ぐにボクの舌は絡め取られた。
大人のキスだと思った。
ボクはボーッとした頭で叔母ちゃんの話を聞いた。
ボクが幼い頃からの言動やこの間の葬儀の時のボクの視線を総合して考えて、叔母ちゃんはボクの叔母ちゃんへの想いが今も続いていることを女の勘で感じ取っていたという。
だから葬儀が終わったら、ボクが叔母ちゃんのところへ来ると確信していたらしい。
実際、アズサからの連絡が無ければ、ボクはきっと叔母ちゃんを訪ねて行っていたのではないかと思う。
ところがいつまで経っても叔母ちゃんのところにボクが現れる気配は無く、叔母ちゃんはアズサの話から何が起こったのかを知ることとなったらしい。
「叔母ちゃんのこと、今でも好きでしょう?」
そう言われて、ボクは咄嗟に否定できなかった。
「アズサのこと好きなの?」
その問いにも叔母ちゃんから聞かれるとボクは直ぐに肯定できなかった。
曖昧な返事のままでいると、
「バスルームを借りるわよ」
叔母はそう言うと、ボクの返事を待たずに脱衣所へと向かった。唖然としていると、
「どうしたの?トモくんも来るのよ」
と呼ばれた。
言われるがままにバスルームに向かうと、素っ裸の叔母の後ろ姿が見えて、バスルームの扉の向こうへと消えて行った。
その姿を見た途端、ボクは暴走モードに切り替わってしまい、着ているものを全部脱ぎ捨てると叔母の後を追った。
お湯は溜めていなかったので、そこにはシャワーを浴びている叔母の姿があった。
熱に浮かされるように叔母に身体を洗われて、カチンコチンになったペニスを叔母にニギニギされるとボクはあっという間に果ててしまった。
あまりの早さにボクは恥ずかしくなって真っ赤になってしまったが、叔母は優しく石鹸でボクのモノを洗い流してくれて、
「先にベッドへ行ってて」
と、2人しかいないのにボクに耳打ちした。
バスルームで一度放出したボクは、少し落ち着きを取り戻して、
"アズサに知られたらどうしよう・・・"
などと心配していたが、アラフォーとは思えない叔母の美しい裸を間近に見てしまった後では、理性を働かせるには無理があった。
叔母はバスタオルを巻いてバスルームから戻ってくるとボクを促してベッドに座らせた。
そしてゆっくりとボクの身体を押し倒してゆくと、ボクの唇を妖艶な舌の動きで舐めた。
「トモくん、舌を出して」
叔母に言われるままに舌を出すと、叔母はフェラをするように首を前後に動かしながら突き出したボクの舌を吸った。
気持ちよかった。
ボクのモノはそれだけで直ぐに復活してしまって、いつの間にかバスタオルを取って覆いかぶさってきた叔母の下腹部を押し上げた。
「やっぱり元気ね」
そう言うと、叔母はボクの屹立したモノに手を添えながらボクの胸に唇を移した。
叔母のポッテリとした唇がボクの乳首を吸うように押し付けられた。
ふくよかなおっぱいが手の届くところにあって軽く揉んでみた。
何度もオナニーのおかずにしていた乳房がボクの掌の中にあった。
ボクは夢中で叔母の背中に腕を回して引き寄せようとすると、叔母は身体の向きを変えてボクの顔の上に跨ってきてシックスナインになった。
目の前に叔母の亀裂が晒されて、ボクは思わず見入ってしまった。
アズサと違ってビラビラが大きくて少し黒ずんでいたが、パックリと開いた大人の割れ目は赤くて、早くも愛液で濡れて光っていた。
ボクはそろそろと手を伸ばして叔母の亀裂に沿って指を這わせてみた。
そうしているうちに叔母が腰をボクの顔に近づけてきたと思ったら、ボクのモノはパクリと何か温かいものに包まれた。
「あっ!」
ボクは思わず、女の子が喘ぐような声を出してしまった。
叔母の舌遣いはそれほど巧みで、アズサのフェラとは格段に気持ち良さが違った。
ボクも叔母のクリトリスに舌を伸ばし、必死に応戦しようとしたが、叔母の舌技には勝てずにあっと言う間に叔母の口の中に放出した。
叔母はそれでもボクを口に含み続け、叔母の口から解放された時、ボクは精液をすっかり吸い取られていた。
叔母がボクの隣に横になって、ボクの顔を覗き込んだ。
「昔からね、トモくんに迫られたら私、きっと抗えないと思っていたの」
「叔母ちゃん・・・」
「お葬式の時、ずっと叔母ちゃんのこと見てたでしょう?」
「それは・・・」
ボクが話そうとするのに被せるように叔母は言った。
「嬉しかったわ」
「叔母ちゃん・・・」
ボクは"叔母ちゃん"としか言えなかった。
「アズサはこんなことしてくれないでしょう?」
舌を絡めてきたことか、濃厚なフェラのことかわからなかったがボクは素直に頷いてしまった。
叔母の細い指でボクのものは再び握り締められ、アズサに悪いと思いながらも、妖艶な大人の女性の微笑を浮かべた叔母の誘惑には勝てなかった。
叔母の手の中で復活を遂げ、ボクは叔母に覆いかぶさると唇を吸った。
途端に叔母の舌が伸びてきたので吸ってみた。
そうすると叔母のエッチモードにスイッチが入ったようだった。
叔母には言えないし、後から知ったことだけれど、それはアズサも同じだった。
アズサの身体で覚えた性感帯を叔母にも試してみる。
「ああ、いいわ」
叔母が艶かしい声を出してボクは勇気付けられた。
流石に親子だけあって感じるところも同じらしい。
ボクはアズサが喜ぶ手順で叔母の喉の下からおっぱいを通って脇腹から腰骨へと唇を這わせて、草むらに到達してからは包皮を指で押し上げて敏感な突起に舌を押し当てた。
「トモくん、それいい!」
叔母は自分で自分のおっぱいを揉むようにして腰をくねらせた。
念入りにクリを舌先でほぐした後、すっかり愛液で濡れた叔母の蜜壺に指を入れてアズサが好きなザラザラのスポットを指の腹で擦りあげた。
「トモくん、いきなりはダメよ!叔母さん、久しぶりなんだから・・・」
そう言いながらも叔母の腰は持ち上がってきて、
「はっ、はっ、はっ、はっ、あぅ!」
と声を出して身体を震わせると腰がストンと落ちた。
叔母の亀裂から噴出した大量の愛液がベッドのシーツに広がった。
叔母はしばらく身体を何度も震わせながら"ハァ、ハァ"と息を整えていたが、やがて一段落するとベッドに仰向けになって膝を立てるとボクを誘った。
「トモくん、来て」
ボクは叔母の脚の間に覆いかぶさると痛いほどに屹立した肉棒を叔母に押し当てた。
叔母の顔を見てみると軽く頷いたので、ボクは一気に叔母に入っていった。
「あぁ、いい!」
叔母が白い喉を見せるように顎を上げて仰け反ると、ボクの根元の方が締め付けられた。
アズサのようにきつく締め付けてくるのではなくて、叔母の中は何かが蠢いているようだった。
叔母の脇の下腕を差し込んで背中の方からしがみ付くように叔母の肩に手をやって腰を少し動かすと、ボクはもう我慢ができなくなって、無我夢中で叔母の中で暴れまわった。
「トモくん、大きい!」
叔母はボクの背中に腕を回して抱きついてきたかと思うとボクの腰に叔母の脚が巻きついてきた。
叔母の一番奥まで入った状態で、ボクは叔母の身体にしがみつき擦り付けるように腰をグラインドさせると、叔母は歓喜の声を上げた。
「あぅ、また、イッちゃう、あぁ、あぁ、あー!」
「叔母ちゃん、ゴメン、もう出そう・・・」
ボクが腰を引いて抜こうとすると叔母はボクの腰に回した脚にいっそう力を込めて、
「今日は大丈夫だから・・・、中で大丈夫・・・」
そう耳元で囁かれた。
それを聞いたボクは狂ったように腰を振ると、
「あ゛ーっ!!!」
ボクと叔母の絶頂の声が重なった。
その日、ボクは生まれて初めての中出しを経験した。
三度目の射精だったのに、ボクのペニスはいつまでもビクビクと脈打ち続け、それまでに経験したことのないほどたくさんの精子を放出した。
叔母の身体もびっくりするほど痙攣していて、いつまでもボクのペニスを締め付けていた。
「叔父ちゃんと結婚して、トモくんが叔母ちゃんと一緒にお風呂に入ったときのこと、覚えてる?」
ボクは照れ臭くて曖昧な返事をした。
「あの時ね、トモくん、もうおっきくなってたんだよ」
「え?それって・・・」
「そう、これ」
叔母はボクのジュニアに軽く触れた。
「あの時、"ああ、男の子なんだなぁ"って思って、正直、叔母ちゃん、少し濡れちゃった」
叔母の告白を聞いて、ボクの方がなんだか恥ずかしくなってしまった。
ボクが黙っていたので、叔母は1人で話を続けた。
「大学に入って、アズサは変わったわ。あ、一段と女らしくなったって意味だけど」
「・・・」
「お相手がトモくんだということは直ぐにわかったわ。アズサがトモくんの話をする時、電話の声が1オクターブ高くなっているから」
ボクが叔母の顔を見られずにいると、
「アズサとエッチしたの、大学に入って直ぐでしょう?」
と聞かれて、ボクは顔が赤くなるのを感じた。
認めてしまったのと同じだと思った。
「それまでのアズサはね、"キャリアウーマンになるんだ"ってずっと言ってたの。知ってた?」
ボクが首を横に振るのを見て叔母は続けた。
「それがね、最近では学校が終わってからクッキングスクールに行きたいとか言い出して・・・。アズサが大学で何のクラブに入ったか知ってる?」
「茶道部って聞いたけど・・・」
「そう、トモくん、日本的な女の子が好きでしょう?」
ボクが思わず頷いてしまうと、
「女って好きな男の人の為なら平気で自分を変えられるの」
と叔母は続けた。
でも、ボクにはどうして叔母がこんな話をするのか解からなかった。
正直言うと、"どうしてボクなんかを"と思いつつも"親子で好みは似るのかな"などと思ってみた。
「あの、叔母ちゃん、どうも話がよく見えないんだけど・・・」
そう言うと、叔母は片目を瞑ってみせて、
「そうよね。解かるわけないわよね」
と言って一人で頷いていた。
急に話は変わって、叔母が唐突に言った。
「叔母ちゃん、まだ39なの」
自分の歳のことを言っているのはわかったが、何が言いたいのかは解からなかった。
ボクが腑に落ちない顔をしていたからだろう、叔母ちゃんは話を続けた。
「オンナ盛りってわかるかな・・・」
ボクが曖昧に頷くと、
「男の人の肌が恋しい夜もあるけど、出会い系なんかで知らない人に会うのはイヤだし、普通にしていても新しい出会いなんてないの」
叔母ちゃんほどの美貌があれば、街を歩くだけで男がついてきそうな気がしたが、口には出さず黙っていた。
そんなボクを見つめながら、叔母ちゃんは核心的なところに言い及んだ。
「だから、トモくんにお相手して欲しいの」
これにはボクも驚いた。
「どうして、ボクなの?」
「全く好意も何も無い相手だと・・・、ね?オンナってデリケートなのよ」
「"好意"って叔母ちゃんが好きな人のこと?それとも叔母ちゃんを好きな人のこと?」
思わずボクは聞いてしまった。
「トモくん、それを女に言わせる?」
そう言って思わず吹き出していたけど、ボクが真顔のままだったので、叔母ちゃんも真剣な表情に戻って少し視線を外すと、
「どっちもよ」
と少し照れくさそうに言ってくれた。
それからボクはアズサに内緒で叔母ちゃんと月に一度か二度会うようになった。
アズサと鉢合わせをしないように、叔母がボクのマンションに来たのはそれっきりで、いつも会うのはホテルだった。
交わった後、叔母はよく言った。
「アズサがトモくんの事、好きになるのはわかるの」
叔母ちゃんはそう言うけど、ボクには解からなかった。
なぜかと聞いてみても叔母は微笑むだけで教えてくれない。
叔母の性欲は貪欲だった。
アズサがあっさりした和食系なら叔母はこってりとした洋食系だった。
たっぷりと時間をかけて、何度も叔母は絶頂に達した後、ボクにも二、三回射精させた後で、グロッキー気味のボクが、
「叔母ちゃん、少し休ませて・・・」
と音を上げると、叔母は黙ってボクの股間に顔を埋めた。
濃厚なフェラを受けてもボクは勃ち上がれずにいると、突然それは襲ってきた。
「!!!」
叔母の指はズッポリとボクのアヌスに差し込まれ、前立腺を刺激してきた。
「ああ!」
反射的にフル勃起したボクは瞬く間に叔母の濡れそぼった蜜壺に吸い込まれ、叔母がボクに跨ったまま腰を振った。
「トモくん、いい!」
叔母はそのまま昇天し、ボクは次の射精を迎えた。
ぐったりとした叔母は上半身を倒してボクに覆いかぶさると、余韻を楽しむかのように身体をビクビクと震わせていた。
叔母が好きな前戯をアズサにこそっと試してみたら、アズサの乱れようも激しくなって、和食系から軽めの中華になった。
「トモくん、なんだかすごぉーい!私、開発されちゃってるぅ!」
何も知らないアズサは絶頂の後、ボクの脇腹におでこを押し付けてきて余韻を楽しむかのように甘えてきた。
"か、可愛い・・・"
アズサの背中に手をやって撫でてやる。すべすべのお肌が掌に触れて気持ちがいい。
「アズサ、舌を出してみて」
不思議そうな目をしながらもボクに従うアズサ。
ボクは叔母がしてくれたように、アズサの舌先にボクの舌先を摺り合わせた。
それから唇が触れるか触れないかの距離でお互いの息遣いを感じていると、アズサ舌が唇の間から見え隠れし始めた。
叔母がボクのペニスにしてくれるようにアズサの尖った舌を吸い込むと、すでに反応を見せ始めた敏感な蕾に指を当てた。
「んーっ!」
舌を吸い込まれたままアズサは喉の奥から声を発した。
指の動きを早めていくとアズサは顎を上げて仰け反った。
ボクの唇からスルリとアズサの舌が抜けてアズサは悶え始めた。
「トモくん、またイッちゃう・・・、あー、イクッ・・・、ねぇ、いい?イッちゃうけど、いい?」
「いいよ、でもイク時は言ってね」
叔母がボクに言ったようにアズサに言うと、
「あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、もうダメ!イッちゃう、あー、イク!イク、イク、イクッ!!!」
魚が跳ねるようにアズサの身体が反り返るとアズサは喉の奥から"ぐぅ"という声を発して昇天した。
硬くピンと勃っていたピンクの乳首が見る見る萎んでいった。
身体の痙攣が治まったアズサは、
「トモくん、すごぉーい」
そう言いながらも、
「他の女の人にこんなことしてないよね?」
と言ってきた時には女の鋭い勘に舌を巻いた。
「そんなわけないじゃん」
平静を装ってボクが言うと、それ以上疑う様子もなく、
「私たち、相性いいよね」
と、何も知らないアズサはが無邪気な目をしてボクに言った。
まさか母親から学んだことを娘にしているとも言えず、ボクは曖昧な笑みを浮かべながらアズサの長い髪を撫でてやった。
親子だと顔だけではなくて、エッチで感じるところもアクメの瞬間も似るのだと心の中で思っていた。
叔母もコッテリ系ばかりではボクが食傷気味になってしまうと知ってか知らずか、ボクにその兆候が現れると遠慮してアズサに任せてしまう辺りが大人の女性だ。
アズサと別れるように叔母から言われたことは一度も無い。
それだけにボクの中では罪悪感みたいな感情がいつも渦巻いていた。
叔母が本気を出せば、ボクみたいな小僧を狂わせるのは赤子の手を捻るようなものだとも思うのだけど、ボクが叔母から離れられない絶妙な加減で距離感を保っているのだと思う。
ボクのお相手が自分の娘であるということも叔母に歯止めを掛けている一因になっているのかもしれない。
叔母がボクを一気に復活させた時のことを思い出して、こっそりそれをアズサに試してみたことがある。
アズサに何度か中イキをさせてぐったりしたところで、ボクはアズサのおっぱいに顔を埋めた。
「トモくんはおっぱいが好きね」
そう言って母親のようにボクの髪を撫でるアズサはすっかり満足していた。
第一ラウンドではピンピンに勃ち上がる乳首も少し硬くなった程度だ。
そこでボクは、指を亀裂に這わせておつゆが少しずつお尻の方に垂れてきたところで薬指をアズサの菊門に滑り込ませた。
「!!!」
アズサの身体がビクッと硬直して、
「トモくん、イヤ!そんなことやめて!」
アズサは腰を引いて逃げようとしたが、ボクはガッチリとそれを抑え込んで半分シックスナインのような形になった。
叔母がボクにしたようにゆっくりと指を抜き差しして徐々に刺激を強くしていくと、
「トモくん、ダメ!そんなのやめて!」
と口では言うものの、敏感な蕾は大きく膨らんで自然に包皮から顔を覗かせていた。
ボクはそれをチュウチュウと優しく吸ってやると、アズサは一層苦しそうに声を上げた。
「トモくん!ダメだってば!あん!ダメだってば・・・、あー・・・」
ボクは試しに中指を膣内に差し込んで蜜壺と菊門の両方を攻めて抜き差しした。
「あ゛ーっ!!!トモくん、いや、こんなのいや!やめて、やめて、やめて!あ゛ーっ、やめっ・・・」
そう言った途端、アズサの身体全体に痙攣が走り、アズサは顎を上げて白い喉を見せながら、白目を剥いて気を失っていた。
噴き出たアズサのお汁でボクの手はびっしょりだった。
ほんの1、2分で目を覚ましたアズサはボクに食って掛かった。
「トモくん、酷いよ!」
ボクはそれには答えずにアズサの細い身体を抱きしめるとアズサは急に大人しくなって、ボクの耳元で囁いた。
「トモくん、怖いよ・・・。私、"トモくん中毒"になっちゃうよ・・・」
少し腕の力を緩めてアズサの背中を撫で続けていると、アズサは子供のようにいつの間にかボクの腕の中で寝息を立てていた。
アズサに肩を揺すられて、ボクは目を覚ました。
アズサの穏やかな寝息を耳元で聞くうちにいつの間にか眠ってしまったらしい。
「どうした?」
ボクがアズサに問いかけると、アズサは急に笑い出した。
「と、トモくん、アハ・・・、あのね、アハハハ・・・」
アズサがひとしきり笑って、ようやく落ち着くと、何だか恥ずかしそうにモジモジしている。
「どうした?」
改めて聞くとアズサはやっと口を開いた。
「あのね、トモくん・・・。私、腰が抜けたみたい・・・」
そう言った途端、アズサは再び笑い始めた。
人間は驚きすぎると笑うのだと思った。
「痛むの?」
「ううん、でも全然力が入らないの」
「ほら、まずは上体を起こしてごらん」
そう言って上体を起こしてやって身体を支えながらベッドの上に座らせてやると、アズサはやっと落ち着いて笑うのをやめた。
やめたというよりも治まったという方が正しいかもしれない。
「アズサ、大丈夫?」
聞いてみるとアズサはコクリと頷いて、ようやく長い脚をベッドの淵から出して立ち上がった。
「驚いたぁ・・・。腰が抜けるってこういうことなんだぁ・・・」
「驚いたのはこっちだよ」
そう言いながらゆっくりとアズサに顔を近づけていくと、ボクたちは甘い口付けを交わした。
アズサは僕と母親のことを知らないから無邪気に母親との会話ボクに話してくることがよくあった。
何気ない話題でも、叔母の話がアズサの口に上るたびにになるたびにボクはどうしようもなく嫌な汗をかいていた。
「ねぇ、トモくん。アズサと叔母ちゃん、どっちの方が気持ちいい?」
一度だけ叔母にフェラをされながら聞かれたことがある。
ボクが黙っていると叔母はお口からボクのものを出すと、
「トモくんはまだまだね。女にそう聞かれたら、嘘でも聞いてきた方の女だって言わなきゃ駄目よ」
そう言ってデコピンをするようにボクの亀頭を指で弾いた。
「いたっ!」
ボクは思わず腰を引いたけど、叔母にガッチリと押さえ込まれていて、次の瞬間には叔母のお口の中に呑み込まれていた。
その日の叔母はちょっと意地悪だった。
自分は巧みに何度も絶頂に達するくせに、ボクにはちっとも放出させてくれなかった。
ヌルヌルの叔母の膣の中でボクはふやけてしまいそうだった。
もう我慢できなくて、叔母の上に覆いかぶさって奥まで挿れて激しく腰を振ったが、昇り詰めるまでにスルッと抜けてしまったり、もう少しというところでペニスの根元を叔母の指でキュッと押さえられて射精を止められてしまった。
寸止めを何度も繰り返されてボクの勃ちが悪くなってくると、叔母は伝家の宝刀を抜いてボクの前立腺を刺激し、ボクは瞬く間にカチンコチンに蘇った。
ボクは正常位で叔母の中に入って再び腰を振った。
一番深い奥を突きながら叔母の耳元でボクは囁いた。
「叔母ちゃん・・・、叔母ちゃんの方が気持ちいい・・・、もうイカせて・・・」
叔母はようやく満足したように微笑んだように見えた。
そうすると叔母は脚をボクの腰に巻きつけてきて、ボクの腰の動きを止めた。
次の瞬間、叔母がボクの肉棒をギュウギュウ締め付けてきて、根元から先っぽに移動するように絡み付いてきた。
自分でピストン運動をするよりも遥かに大きな快感がボクを突き抜けると、物凄い射精感がボクを襲った。
ゴムをつける暇もなく、ボクはだらしなく叔母の膣内に放出していた。
ぐったりとして叔母に入ったまま抱きついていると叔母の膣が再び動いて屹立させられ、搾り取られるようにもう一度果てた。
叔母からは離れられない。ボクはそのとき思い知らされた。
そう思っていた。
それからしばらく経って、アズサとのまったりとした午後を過ごしていると腕枕をしたアズサが語るともなしに言った。
「お母さんのことなんだけど・・・」
「うん?」
ボクは一瞬身体が強張ってしまった。
「何だか少し元気がないの・・・」
「そうなの?」
「うん・・・」
「何か思い当たることでもあるの?」
アズサは少し言い淀(よど)んでいたが、意を決したように言った。
「お母さん、妊娠してるんじゃないかなぁ」
ボクは思わず言葉を失ってしまった。
狼狽えぶりを悟られないように、ボクは努めて声を落ち着かせようとしたのだけれど、自然にどもってしまった。
「ど、どうして、そう思うの?」
何も知らないアズサはボクが単に驚いているだけだと思ったのか、言葉を続けた。
「お母さん、最近ずっとウキウキしてる感じだったんだけど、ここ数日元気がないの・・・」
「でも、だからと言って妊娠って言うのは飛躍しすぎじゃ・・・」
ボクは声が少しムキになっていることに気がついて、声が尻すぼみになった。
「私、見ちゃったんだ」
「何を?」
「妊娠検査薬の箱が捨ててあるの」
「・・・」
ボクには思い当たる節がなくもなかった。
ボクは避妊を完全に叔母ちゃん任せにしていた。
だから、もしそうだとしたらきっとボクの子だ。
その日はもう叔母のことが気になってしまってどうしようもなかった。
叔母と会う時は決まって叔母が連絡をしてくるのだけど、その時はボクから連絡した。
「もしもし、叔母ちゃん?」
「あら、トモくんが電話をくれるなんて珍しいわね」
気のせいか、電話の向こうの叔母の声が少し暗い感じがした。
「あの・・・、叔母ちゃん、今日会えないかな?」
ボクがそう言うと、
「うん、叔母ちゃんもトモくんに会いたいと思ってた」
と言ってくれて、ボクたちは待ち合わせをした。
いつものことではあるが、2人きりで話をしたかったので、会ってから直ぐにホテルに向かった。
いつもだったら直ぐにシャワー浴びてベッドで抱き合うけど、ボクは叔母をベッドに座らせると話を切り出した。
「あの、叔母ちゃん・・・、ボク、責任取るから」
思い切ってそう言った。
「何のこと?」
叔母が不思議そうにボクを見るので、
「その・・・、子供が出来たみたいだって・・・」
と叔母のお腹に視線をやりながら言うと、叔母は大きく溜息を吐いて、
「だから気を付けてって言ったじゃない」
と少しボクを責めるように言った。
ボクが何も言えずに項垂れていると、
「それで?あの子は産むって言っているの?」
と言われて話が噛み合っていないことに漸く気づいた。
「あの・・・、アズサじゃなくって、叔母ちゃんのことなんだけど・・・」
「私?」
ボクが頷くと叔母ちゃんは急に笑い出した。
「何がおかしいの?」
「それ言ったの、アズサでしょう?」
ボクが再び頷くと、叔母はようやくニッコリと笑うと、
「大丈夫よ」
と言った。
叔母の生理が遅れていたのは事実で、叔母自身も少し心配になったので調べてみたが、結果は陰性だったという。
調べてみたすぐ後で生理があって、ボクと会ったその日も生理中だったけど、ボクをお口で慰めてくれるつもりできてくれたらしい。
「安心した?」
ボクが思わず頷いてしまって、そのことに気づいてどう反応したものか困っていると、叔母は優しくボクの頭を自分の胸に引き寄せて言った。
「トモくん、責任とってくれるんだね。ありがとう。叔母ちゃんとっても嬉しい」
「・・・」
「欲しかったな、トモくんの赤ちゃん・・・」
叔母の胸に抱かれながらそう聞いた時、ボクはジンと来てしまった。
アズサはボクにしょっちゅう、"私のこと好き?"とか"私のこと愛してる?"と聞いてくるのだが、叔母は一度もそう言う類のことを聞いてきたことがなかった。
当然に、叔母からもボクに対する気持ちを聞かされたこともなかったので、ボクは叔母がそう言ったことに少し驚いていた。
「アズサとは一緒になるの?」
ボクが答えられずにいると、
「今日で最後にしようか」
と叔母は言った。
冗談かと思いながらも叔母の顔を見ると叔母の目はマジだった。
「叔母ちゃん・・・」
「子供ができちゃったかもしれないと思ったとき、思ったの」
「?」
「トモくんの子供を私が産んで、トモくんとアズサが一緒になったら、その子はアズサの兄弟で、トモくんの連れ子で、娘婿の子供だったら、私の孫?そんな風に考えたら、これ以上は許されないと気づいたの」
「そんな・・・」
「あの子は、トモくんのこと、大好きよ」
「・・・叔母ちゃんは?」
叔母がそんなことを言うとは思っていなくて、驚いて思わず聞き返してしまった。
叔母はボクの問いには答えずに、
「さぁ、脱いでと」
と言ってボクの着ているものを脱がせると、ボクの股間に顔をうずめた。
夢のような甘い時間が流れ、ボクは叔母の舌と唇に翻弄された。
「やっぱり我慢できない」
叔母はそう言うとベッドにバスタオルを敷き詰めると、素っ裸になってボクの腰に跨った。
ボクの怒張した肉棒は叔母にスルっと呑み込まれた。
一番奥まで達すると、叔母は上体をボクの方に倒してきて両手で包むようにボクの頬に手を当てた。
妖艶な叔母の唇が少し開いて下が伸びてきた。
ボクも舌を伸ばすと叔母は舌の先と先と触れさせて刺激した後、唇をすぼめてボクの舌を吸い込んだ。
脳天を突き抜けるような快感に包まれて、叔母の膣に包まれたボクの男根は硬さを一層増した。
「ああ、トモくん、いい・・・」
唇を離した叔母が呟くように言って、ボクのものをギュウギュウと締め付けてきた。
ボクは叔母の腰に手をやって下から突き上げると、叔母は仰け反って悶えた。
「トモくん、それ・・・、それ、いい!」
ボクはどんどん腰の動きを加速していった。
すると叔母は上体を起こして、腰を密着させると激しく擦り付けるように腰を前後に動かしてきた。
ボクも上体を起こして向かい合って抱き合って、叔母のわき腹に手を這わせながらビンビンに膨らんだ乳首を吸い上げると、叔母はそのまま"かっ!"と声とも息とも区別のつかない絶頂の声を上げて仰け反った。
叔母の膣はボクを締め上げたままだったが、叔母は顎を上げたままボクの腕の中で失神していた。
叔母の身体をゆっくりと押し倒すようにし、ベッドに横にならせてボクはピストン運動を再開した。
叔母は零れそうになった涎を吸うような音と立てて目を覚まし、再び肉棒の快楽に酔いしれた。
「トモくん、叔母ちゃんイッちゃう。あー、また、イク、イク、イク!!!」
何度も叔母が絶頂に達した後で、ボクは激しく脈打つと叔母の柔らかい襞に包まれながら放出した。
叔母とはそれっきりだ。
アズサは卒業を控え、今では夫婦のようにボクの部屋で暮らしている。
たまに叔母を交えて食事をしたりもするが、叔母はあくまでもボクの恋人の母親だ。
たまにボクが叔母に視線を送っても、叔母の反応はアズサの母親としてのものだった。
時々、あれは夢だったのではないかと思うこともあるけど、叔母が屈んだ拍子などに襟からブラジャーに包まれたおっぱいが覗くと、ボクの股間は熱を帯びて今でもズキンと反応してしまうのだ。
それと心配事が、もう1つある。
ボクとアズサに子供ができて・・・、娘だったらどうしよう・・・。
叔母やアズサに似てしまったら、ボクの中の暴走モードのスイッチが入ってしまうかもしれない。
スイッチが入ったらきっともう止められない。
親子丼はもう美味しくいただいてしまった。
禁断の果実の味を知ってしまったボク・・・。
親子孫丼を食さずにボクはいられるか・・・、ボクには自信がない。
- 関連記事
-
- アナニーを極めていつでも絶頂にイケるようになったけど人生が終わったwww
- 旅館にいた頭の悪そうなヤンキーカップルがお風呂でケンカしていた
- 一人旅できた奥飛騨温泉郷の混浴で綺麗な女性と一緒になった
- とびっきり美人の妻の友達とやっちゃった話
- スタバで見かけた童顔巨乳の可愛い子から逆ナンされた
- サークルメンバーで宅飲みした時に放置プレイされた
- 職場で知り合った箱入りのお嬢様のヌードを覗きみた話
- 大好きな叔母と、叔母に瓜二つな従妹と葬儀で再会した母娘丼体験
- 付き合う意味も知らない箱入りお嬢様にバックで挿入
- 妻が不倫相手の男と不倫してハメ撮りサイトに写真投稿 その3
- フル勃起全盛期に友達の家で酒を飲んで女友達を犯す
- バイト先の居酒屋のカウンターに居た女の子ナンパしてセックス
- 彼女をイカす事が出来ずに教授に寝取られる俺
- 彼女が先輩に犯されてる横で先輩の彼女とセックス
- 彼女とエッチした数時間前に彼女が先輩と浮気
≪ マッサージ師のおじさんの手の動きがどんどん怪しくなっていって、結局犯されちゃった | HOME | 割り切った関係を希望する出会い系の人妻をチンコで夢中にさせたった ≫
≪ マッサージ師のおじさんの手の動きがどんどん怪しくなっていって、結局犯されちゃった | HOME | 割り切った関係を希望する出会い系の人妻をチンコで夢中にさせたった ≫
-
スワッピングして淫乱になった結果、夫が大喜びしてる件 (06/02)
-
彼女が口内射精されてお掃除フェラまでしてる現場を目撃した件 (06/01)
-
飲み会のあと欲情した年上のパート女性とハメハメしたったwww (06/01)
-
隣のムッチリ人妻が泥酔しとったからエチエチなことしたったwww (06/01)
-
童貞って可愛いよね?wwwwwwwww (05/31)
-
痴漢されて感じちゃったwwwwwwwwwwwwww (05/31)
-
巨乳CAはお掃除フェラもしてくれる抜群にエロいイギリス人女性やったwww (05/29)
-
大学時代のメンバーと飲んでナマでエッチしちゃった (05/29)
-
工事現場の男性をオナニーのおかずにした結果がこちらwwwwwwwww (05/29)
-
彼女が元カレとのセックスで逝き狂ってるんだが・・・ (05/29)
-
不倫にハマった人妻の私・・・ (05/27)
-
セックスレスだったから新入社員の男の子と車の中で致した話 (05/26)
-
手コキで出しちゃったから童貞卒業できんかったわwwwwwwwwww (05/26)
-
若くて元気のいい童貞君を逆ナンパしてじっくりと教えてあげた話www (05/26)
-
お姉ちゃんのマン毛抜いたら怒られた話wwwwwwww (05/26)
-
ホテルの宿泊券が当たったから母親と行った結果→アナルセックスに発展www (05/25)
-
男友達とドライブに行った帰りに中出しエッチしちゃった思い出 (05/25)
-
欲求不満な人妻事務員さんとセックスしたら感度良すぎwww (05/23)
-
高身長のツンデレ貧乳OLと致した話 (05/23)
-
フライト中にトイレで不倫セックスwwwwwwwwww (05/22)
-
幼馴染とのカーセックスで童貞卒業した時の話を聞いてくれ (05/22)
-
夫の出張中に不倫したら発情しちゃってマッチングアプリで・・・ (05/22)
-
入院中に俺のオナニーを覗く女とセックスしたったwww (05/22)
-
専務のチンコ舐めて中出しさせて仕事もミスを帳消しwwwwwwwwwwwww (05/21)
-
37歳の人妻事務員を酔わせてラブホにwwwwwwwww (05/20)
-
幼馴染の夫婦とハメ撮りスワッピング! (05/16)
-
娘のアソコをお医者さんごっこだと舐める男の子と・・・ (05/15)
-
スイミングスクールのコーチと人妻のセックス目撃しちゃったwww (05/15)
-
ルックスがイマイチだけどフェラテク良くてスケベだから◎wwwwwwww (05/15)
-
旅先で意気投合した人妻と朝までヤッた話 (05/15)
フェラ 中出し 生挿入 人妻 クンニ 浮気 口内発射 キス OL オナニー アナル 不倫 職場 複数 熟女 女子大生 出会い系 初体験 寝取られ 寝取り 絶頂 淫乱 彼女 童貞 巨乳 妻 美人 ごっくん 手コキ 処女 痴女 おっぱい カップル 近親●姦 風俗 M女 夫婦 乱交 セフレ ラブホ 3P 射精 年上 女友達 おもちゃ 露出 変態 泥酔 野外 年下 旅行 撮影 お酒 手マン 69 学生 風俗嬢 調教 潮吹き ナンパ 目撃 覗き バイブ アルバイト 筆おろし ホテル 成り行き 先輩 彼氏持ち 寝取らせ 巨根 レ●プ 姉 三十路 妹 ナース お掃除フェラ 彼氏 騎乗位 ハメ撮り パイパン 温泉 トイレ 四十路 本番 お風呂 アナルセックス 青姦 後輩 顔射 バック 兄妹●姦 スワッピング SM デリヘル アナル舐め レズ 友達 同級生 ギャル 輪姦 同僚 正常位 羞恥 ハーレム 上司 カーセックス ヤリマン サークル 妊娠 マッサージ jc 再会 悪戯 姉弟●姦 外国人 病院 パイズリ 四つん這い 想い人 母 ローター 告白 お持ち帰り 4P ビッチ イケメン 嫁 車内 M男 貧乳 ノーパン ローション 女教師 ソープ 学校 Hな体験談 合コン 夏休み 友達の彼女 ホモ 元カノ 入院 公園 睡姦 バツイチ ゲイ 部活 脅迫 愛撫 失神 鬼畜 夜這い 早漏 海外 立ちバック カラオケ コスプレ 母子●姦 S女 AV 幼馴染 ノーブラ 一夜限り 家庭教師 プール 浴衣 結婚 拘束 混浴 異常 王様ゲーム 大学時代 イラマチオ 男友達 動画 兄 従姉妹 ぶっかけ 剃毛 水着 お漏らし 見せつけ 子持ち スカトロ 媚薬 五十路 包茎 浣腸 メンヘラ 義姉 セックスレス 緊縛 教師 会社 セクハラ ピル 制服 言葉責め 海 罰ゲーム ブス 部下 姉妹丼 おし●こ 生理 うんこ 逆ナンパ キャバ嬢 義妹 欲求不満 SNS 義母 高校時代 ヤンキー 同窓会 夫婦交換 パート 異物挿入 ぽっちゃり 飲み会 電車 いたずら 忘年会 姉妹 性癖 素股 彼女の友達 フェチ 放尿 パンチラ おしっこ 逆ハーレム 絶倫 童顔 合宿 ハプニング お尻 ニューハーフ 出張 アラフォー 性●隷 友達の母 弟 居酒屋 援助交際 破局 M字開脚 スカ●ロ 娘 未亡人 痴● 父子●姦 近親相姦 チャット 対面座位 父 アラサー 元彼 飲尿 汗だく 友達の嫁 借金 全裸 痙攣 S男 息子 ハプニングバー デート 修学旅行 ヘルス 名器 開発 キャンプ 嫉妬 叔母 元カレ 修羅場 ピンサロ 清楚 女上司 電マ 教え子 デブ AV女優 看護婦 着衣 マンネリ 妻の妹 アナニー 乳首 失禁 筆下ろし 安全日 親子丼 Tバック 義父 パンスト 写メ 遅漏 GW マグロ 焦らし 前立腺 生徒 露天風呂 クリスマス シ●タ 逆レ●プ 正月 親戚 駅弁 W不倫 盗撮 女医 マネージャー 5P オフ会 肉便器 旅館 臭マン 妻の過去 妻の友達 パチンコ 妊婦 インポ 誘惑 座位 テレフォンセックス 無防備 社員旅行 義弟 彼女の妹 モデル ディルド スパンキング 即尺 夏 スナック 母乳 Wフェラ 下着 アブノーマル 顔面騎乗 外人 いじめ ビキニ 友達の彼氏 勃起 姉の友達 双子 青春 愛人 兄嫁 ホームレス 逆夜這い ブサイク 夫 離婚 息子の友達 匂いフェチ バイ 睡眠薬 パンツ 奴隷 ミニスカ 義兄 バレないように ネカフェ 画像 二穴 出産 同棲 イメクラ 店外 枕営業 馴れ初め js 映画館 中イキ パンティ テレクラ 胸チラ ザーメン 面接 目隠し 女装 黒人 黒ギャル ヌード 隣人 ドライブ 従兄弟 保母 ロリ ヤクザ ハーフ メル友 ヤリチン お仕置き 中折れ 犬 M女 ツンデレ コンパニオン 叔父 覗かれ オシ●コ 口移し ホステス 巨尻 塾 イマラチオ 中絶 野外露出 家出 獣● ブルマ ラッキースケベ 肉●器 後悔 くぱぁ オナ禁 誕生日 口内射精 復讐 胸射 ホスト DQN コンビニ 還暦 トラウマ BBQ 妻の母 店員 カップル喫茶 性病 万引き 中国人 家族 ペニバン ご褒美 インストラクター 医者 オタク 彼女の母 後輩の嫁 視姦 危険日 野球拳 尻コキ 元彼女 ネトゲ 留学 盗み聞き コタツ 銭湯 精飲 マングリ返し 遠距離恋愛 更衣室 喘ぎ声 お泊まり 松葉崩し 尻軽 看病 韓国人 朝勃ち 主婦 淫語 女王様 連れ子 痴漢 教室 純愛 ママ友 上司の嫁 彼女持ち ゲーム 近●相姦 性欲 結婚式 クラブ 芸能人 男の娘 萌え メール ソフトSM 友達の姉 援交 大学生 6P 美乳 手こき 妄想 可愛い 事故 お礼 寸止め 甥 母親 CA ガバマン 教育実習生 宅飲み ライブチャット 一目惚れ 掲示板 保健室 ファーストキス お見舞い 妹の彼氏 ホテヘル 先輩の彼女 兄の彼女 患者 キャバクラ 先生 嘔吐 キモ男 座薬 友達の妹 赤ちゃんプレイ テレホンセックス 妹の友達 友達の妻 3P お客 妻の姉 マット 娘の彼氏 バイアグラ マン毛 土下座 屈辱 アメリカ人 授乳 単身赴任 スーツ ジム 夫の弟 先輩の嫁 テニス部 お客さん 仕返し 競泳水着 短小 水中 長身 セクキャバ 裸エプロン 彼女の姉 シャワー お盆 サッカー部 隠し撮り 年末 性接待 剣道部 社長 美容師 M字開脚 相互鑑賞 雑魚寝 敏感 送別会 骨折 パイプカット 性感 姪 発情 アイドル お目覚めフェラ バス 勘違い 診察 オナホ 本気汁 男の潮吹き イメプ 再婚 剛毛 母●相姦 地味 メイド エステ 姫始め ブラコン 花火 義娘 プロポーズ 彼氏の友達 爆乳 文化祭 脱衣麻雀 ストーカー フィストファック 純情 精通 ガーターベルト 閲覧注意 ストリップ H無し 行きずり 真面目 タクシー 手錠 キメセク 兄の嫁 ボーイッシュ 聖水 ハッテン場 医師 尻射 素人 美脚 バスケ部 電話 登山 ワキガ ツーリング 美魔女 フリーター 留学生 おっパブ サウナ 相談 女将 試着室 着替え 卒業旅行 イメージプレイ 夢精 ロリコン ゲーセン 水泳部 Tバック 失恋 夫の友達 秘書 ヌードモデル 陸上部 野球部 麻雀 喧嘩 貝合わせ モテ期 お局 豊満 ギャップ 4P 腐女子 近所 クスコ 近○相姦 マンスジ キスマーク オイル ブログ 鑑賞 就活 寝バック 美少女 姉の彼氏 リスカ マン汁 介抱 売春 風邪 白人 二股 ロシア人 店内 素人童貞 祭り スク水 病室 店長 レースクイーン 海水浴 賭け 若妻 客 ショタ 足コキ 盗聴 クリトリス 女社長 裏切り 恋愛 トコロテン 息子の嫁 パチンコ屋 歯科衛生士 読み物 バスガイド 嫁の友達 再開 ベランダ ゴルフ メガネ 兜合わせ ドレス 美術部 脱衣 花見 顧問 テント ストッキング ヘタレ 粗チン 自撮り 新婚 講師 マニア コンドーム 我慢汁 DV 匂い 後輩の彼女 ヤリコン 痔 駐車場 パンティー 穴兄弟 ギャルママ 酒池肉林 スイミング 質問ある? ヤンデレ 娘の友達 口止め 高嶺の花 失敗 従弟 バー 箱入り娘 図書館 水商売 男子大学生 初フェラ 騙し キャンギャル 放屁 弟の嫁 逆レイプ セックス スレンダー ビンタ 乳首責め 母娘丼 友達の母親 受付嬢 嫁の妹 関西弁 教育実習 ボランティア 夫の上司 団地妻 愚痴 プレゼント チンぐり返し テニス AV男優 放置プレイ 性教育 オムツ 尾行 春休み ピアス マザコン コンパ 性処理 アクメ 性感マッサージ 姉弟相姦 レ○プ ノンケ タンポン 神社 デリヘル嬢 アナルプラグ ルームシェア カメラマン 兄の友達 受験 中国 ゲロ パブ タイ人 スイミングスクール 思春期 見学 見られた LINE 胸キュン 花火大会 陵辱 コーチ 和服 浪人生 女子寮 ポルチオ 残業 お医者さんごっこ 男優 亀甲縛り 男子高校生 寮 脱糞 病気 レイプ 紐パン 着物 親子 健康診断 遊園地 放課後 弟の彼女 拉致 親友 吹奏楽部 家族温泉 シスコン 性転換 スポーツジム 夏祭り 彼女の母親 相互オナニー ストレス 一人暮らし メンズエステ レオタード 騎上位 実家 回春マッサージ スカウト 不妊症 友達の奥さん アヘ顔 搾乳 シングルマザー OL お嬢様 ヒッチハイク SM 継母 マンぐり返し 友達の夫 ゴルフ場 北海道 逆痴● 首輪 日記 PTA 接骨院 寮母 カットモデル 刺青 金髪 生理前 友人 染みパン 玄関 背面座位 ハミ毛 グラドル コテージ 避妊 釣り 鬱 リハビリ アフター 先輩の母 バリ 尻軽女 トリプルフェラ 尻文字 喪服 SM嬢 子連れ ヌーディストビーチ ダンサー 探偵 思い人 初恋 巫女 保育士 ニンフォマニア 添乗員 イベント 鼻フック 韓国 発見 ブサメン 部下の嫁 親 見せ合い 夜勤 VIPPER ケンカ 美人局 膝枕 隠語 BL 欲情 社内恋愛 寝込み パイ射 オカマ 自宅 ぶりっ子 キャンプ場 仮性包茎 マイクロビキニ 老人 同僚の嫁 兄妹相姦 勝負 紹介 ネット 投稿 旦那 スキー場 レギンス 賢者タイム 同僚の彼女 凌辱 女子校生 姉の旦那 一人旅 沖縄 社内 治療 飲● DJ 目の前 夢 逆●漢 アラフィフ 拡張 写真 首絞め 弁護士 独身 台湾 ムチムチ 初夜 スケスケ 手術 女神 便秘 隠撮 M字 同期 jk 彼女もち 姫初め 罵倒 流出 ホットパンツ 台湾人 イジメ 黄金 自転車 喪女 ファザコン パワハラ 挑発 パジャマ エロ動画 スケベ椅子 小悪魔 ハメ潮 キチガイ 唾液 租チン 野菜 オーナー 帰省 ニーハイ 遭遇 両親 性生活 新年会 マジックミラー 倦怠期 恋人交換 寝起き ぎっくり腰 グラビアアイドル 割り切り チンカス 駅 ボーナス わかめ酒